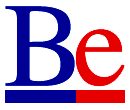
クマさんと BeOS の格闘ページです。たぶん,たまにしか更新しないでしょう。BeOS についての情報は,ぷらっとホームのページとか,Be Lab のページとか,Be-IN のページとか,Be-WebRing のページに行った方がいいです。
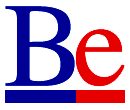 |
BeOS R5 Pro の部屋
クマさんと BeOS の格闘ページです。たぶん,たまにしか更新しないでしょう。BeOS についての情報は,ぷらっとホームのページとか,Be Lab のページとか,Be-IN のページとか,Be-WebRing のページに行った方がいいです。 |
ぷらっとホームで BeOS R5 Pro を買った。こんなマシン構成(というよりは,マザーの VIA チップの問題なのだが)だと,起動時のスプラッシュ画面はディスク認識のアイコン画面がハイライトせずにだんまり。んで,BIOS 設定で Ultra DMA を disable すれば何事もなかったように起動するので,VIA チップを使ったマザーで同様の症状で悩まされている人はお試しあれ。
ひさしぶりの更新。bt848a11.zip(リンクはプライマリサイト)
クマさんは,bt848 ベースなキャプチャカード(Philips のチューナモジュール付き)を持っているのだが(クマさんのハードウエア構成はここ),このソフトを使えば BeOS でもこいつを使うことができる。とりあえず,テレビを見ることができることは確認した。
せっかく vfat のパーティションが簡単にマウントできて,日本語ファイル名(Unicode)が半角カナ(Unicode に半角カナってあったっけ?)まで正常に表示できても,かんじんのテキストファイル(Shift-JIS)が読めないのではどうにもならん。困っていたら,Be Lab のページにエディタがあるのを見つけてもらってきた。KEdit なんちゅー,KDE のエディタみたいな名前だ。HTML のタグをつける機能もあるようだ。
Nifty-SERVE の fbeos mes(2) ネタだったりするのだが,ここに R4 intel 用の sb16 ドライバがあった。どうやってインストールするんだろうと思ったら,解凍して(ファイラからダブルクリックするだけ)インストールスクリプトを実行する(これも同様)だけ。お手軽だ。で,音が鳴らないので README を見てみると「PnP じゃないふるーい sb16 はたぶん認識しないよん。そんなもん使ってるときは,/boot/home/config/settings ディレクトリに sb16_settings というファイルを作って,リソースを指定してちょ。」と書いており,仰せのとおりにしてやっと音が鳴るようになった。
ハイインピーダンス,50cm の SCSI ケーブルを買ってきた。2本で 6000 円もする。12/23 に失敗した SCSI 認識が解決するのでは,と思ったが状況は改善されず,起動しない。しかたなく,SCSI ボードの設定で,ケーブルの末端についた古い 540MB のネゴシエーションを切ると,やっと起動した。しかし,くだんのディスクは認識されないし,起動時のディスク認識も時間がかかる。Linux や Windows NT ではちゃんと認識する。
再度,make に挑戦。
bzip2-0.9.0c.tar.gz
こいつは難なく成功。
patch-2.5.tar.gz
patch コマンドがなかったので,make した。なぜか最初の ./configure でリブートしてしまったが,2 回目で成功。
tar-1.11.8.tar.gz + tar-1.11.8.bzip2.patch
make 途中で,undefined reference... というおなじみのエラーでストップ。しかし,BeOS 買ってこんなことしている人って,ほとんどいないだろうなぁ。本当は,XEmacs 使いたいだけなんだけど。
R4J から gcc を使っているらしいので,Terminal から,gcc --version してみた。2.9-beos-980929 と出た。どこかで見たバージョン表示だな,とさらに gcc --help してみると,Report bugs to egcs-bugs@cygnus.com. という一文が。あれ,egcs だったのか。
で,手元のソースを片っ端から make してみたが,どれも途中でエラーを出して make できん...
R4J になり,SCSI に対応したので,BeOS をインストールすることにした。マシン構成はこちら。一番古い SCSI 3 台目のディスクにインストールすることにした。
SCSI インストール時に引っかかったのは,ケーブル長の問題。CD を読みにいったとたん,ハングして動かない。外付のケーブルが 1m×2 あったのだが,片方を外すと(当然,ケーブルの先のディスクも外れることになる。ちなみに,ふるーい 540MB のディスクが1個あるだけ。)何事もなかったようにインストールできた。Linux や FreeBSD,Windows(95,NT4.0)では何の問題もなかったのだが。
さっそく使ってみた。起動は System Commander 2 から問題なく行える。起動してまず気づくのは,ログイン画面が現れないということ。シングルユーザ向けの OS ゆえだろう。telnet,ftp サーバとして使うときにユーザ名とパスワードを設定するくらい。Optional のソフトもインストールして,使用したディスク領域は 400MB 少々。
メニューは英語だが,設定すれば 106 キーボードは使えるし,WEB ブラウザでも日本語が表示できる。Alt + 漢字キーで日本語入力もできる。
ディスクのマウントはメニューから一発だ。今のところ,vfat のパーティションのみちゃんと使えるようだ。日本語ファイル名も半角カナを含みちゃんと OK。起動時に接続されているディスク,パーティションをすべてチェックするためか,デスクトップ画面が現れてから使えるようになるまで少し時間がかかる。ビデオ CD はうまく認識できないようだ。
ネットワークの設定も,イーサネット,モデムともにとても簡単。95 や NT みたいにいちいち再起動しなくても設定が反映される。UNIX 系 OS,というよりは,マトモな OS なら当然の機能だ。ネットワークの設定をいじるのに休日出勤することもない(ま,休日出勤くらいで済めばよいが,オンライン取引なんかやってるところは,再起動させている間に数億円の損失,なんてこともあるだろう。)。
3D グラフィクスのデモを複数起動してみた。さすがに,このために設計されただけあって,動きはスムーズで高速だ。一太郎を起動させただけで他の機能がほとんど使い物にならなくなる自称マルチタスクサーバ OS とは違う。
Terminal を起動してみた。シェルは使い慣れた bash のようだ。プロンプトは $ だが,もちろん su はできないし,スーパユーザの権限があるみたいなので作業には注意を要する。もちろん,リモートメンテナンスも思いのまま。常識だ。キャラクタベースのリモート機能を使うために,追加で数万円払わなければいけない OS があるというのは未だに信じられない。