名前の通りの内容です。クマさんがインストールした経過を忘れないように書いたものです。たぶん、ちっとも役に立ちません。過去の日記(7月)
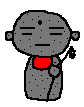
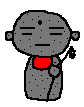
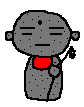
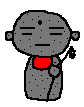
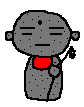
送別会シーズンにもめげず(今は am 2:00)、カーネルを 2.1.123 にする。vfat-jp パッチも 0.8.1pre2 が出ていたのでさっそくいただく。文字コードは EUC を使っているのだが、ちゃんと半角カナが表示される。FD-clone でも大丈夫。samba ではどうなるのかな。2.0.35 の方の communicator を 4.06 にした。日本語化キット(感謝感謝)も導入。タイトルバーに日本語が表示されるようになっている。
土日は,あーでもないこーでもないと windowmaker の設定をやったり,カーネルを 2.1.122 にしたり,gimp の日本語リソースを導入したり,gimp のベースとなる gtk の日本語パッチを導入したりしてすごす。gimp の日本語化は結構ヒットで,英語メニューのときは使う気にならなかったのだが,はまりまくる。これは使えそうだ。対照的に windowmaker はまだバグが取れきっていないようで,機能は確かに豊富でかっこよくすばらしいのだが,日常的に使う気にはなれない。(とかいいながら、日常的に使っている。2.0.35 の方は afterstep)2.0.35 を入れているディスクの残りが 200MB を切ったので,/usr/local/src の容量を調べてみると,何と 750MB もある。
先日入れたプロキシ squid は結構便利。接続していなくてもキャッシュに残っている限りはページを見ることができる。ディスクに余裕があれば,安定版のディスクの方にも入れたいのだが。
ははははは,どうしても,wdm でログインできないときのうきょうで3時間くらい使ったが,その結論はあっけなかった。ワシの Linux (Slack 3.4 & 3.5) ってシャドウパスワードになっていたのね。おおタコだった。configure に --enable-shadow をつけて make して一件落着。ログインできないので,作業はすべて ThinkPad230 から TeraTerm で telnet して行ったのだが,やはりこういうときには UNIX って便利だなと実感する。
一応夏休みをとっているし,台風で風雨は強いしで,前から気になっていた WindowMaker-0.19.3 をインストール。プライマリサイトから必要なライブラリも持ってくる。Software Design 1998年8月号の言いなりになってインストール。おぉ,かっこいい。しかし,メニューの文字が化けてるじゃん。と思ったら,スクリプト一発で各国語メニューになるんですね。おまけに,再起動しなくても変更が反映されるし。
で,気をよくして昼から出勤,おっと,休みなので出勤ではないか。プライマリサイトから面白そうなソフトをごっそり(といっても,FD 2枚分だが)ダウンロード。
日常環境(2.0.35)でも使えそうなので,とりあえず今までキャラクタベースでログインしていたのを wdm(Window Maker 版 xdm)に切り替えるべぇと wdm-0.90 をインストール。ところが,make が途中で止まる。いくらやっても止まる。どうも,configure で必要なライブラリを見つけてくれていないようだったので(それなら最初から configure で止まれよな。make の途中で undefined... なんていわずに)
configure --with-local
でライブラリの位置を明示してやるとやっと成功。/usr/X11R6/lib と include しか探してくれなかったのね。
で,/etc/inittab を書き換えて default runlevel を4にして,/etc/rc.d/rc.4 で /usr/X11R6/bin/xdm の代わりに /usr/local/bin/wdm と書いて再起動。お,けっこうかっこいいログイン画面。ログイン画面で再起動や halt も選べるし,ウィンドウマネージャも選ぶことができる。けっこうすぐれもの,と思ったら甘かった。パスワードを入力するがログインできない。結構安直なパスワード使ってたから,wdm が勝手にはねたのかなぁ...
→そんなことはない。このタコな失敗は翌日解決
xbiff も asmail にかえた。メールが届くと,カラーのアニメーションでメールの到着を知らせてくれる。以前の殺風景な画面とは大違いだ。音も出すことができる。
今日は 2.0.35 上で作業。ebw3(電子ブックビューワ)をインストール。ちゃんとインストールしたはずなのに,辞書のタイトルが出てこない。辞書CDが Joliet らしく,カーネルサポートで無効にできない(2.1 系はできる)のに加えて Joliet 優先でマウントされてしまい,ファイル名がすべて大文字で表示されるのが原因だった。元のソースを書き換えてみるが,なかなかうまくいかない...と悩んでいたら,マウント時に -nojoliet オプションつけてマウントすればよかったんですね。
netscape のプラグインもいっぱい拾ってきたので,CD辞書の鳥の鳴き声も聞けるようになった。
FD-1.03h.tar.gz をインストール。/etc/fdrc をちょこまかと(という割には試行錯誤が多く時間がかかったが)いじり,.tar.bz2 と .bz2 も処理できるようにして,一段と便利。
xtt-1.0.tar.gz をインストール。やたらあちらこちらの設定ファイルを書き換えなければならず,面倒だった割には肝心のフォントの表示は Windows よりかなり汚い。(→などと不満を書いたが、見慣れたらけっこう親しみがわいてきた。でも、netscape のデフォルトのフォントが12 ポイントなのでちとつらいが。150dpi で X 起動したら字は大きくなるけど Tcl/Tk の画面表示が間が抜けたヘンな感じになるし。TrueType のデフォルトのポイント数って変更できないのかな。)
カーネルを 2.1.121 に。vfat-jp パッチのスペシャルバージョン alpha 版が新しくなっていたので,ついでに組み込む。で,make すると,fs/fat/dir.c で ../japanese/japanese.h がないといってエラーで止まる。見てみると,fs/japanese ディレクトリ自体がない。ここはいつものとおり安直に 2.1.120 のソースから丸ごと持ってくる。それでも,最後にエラーで止まる。今度はよーく見てみると,fs/Makefile にパッチが当たっていない箇所がひとつ。手で直す。2.1.119 用のパッチだから仕方がないか。しかし,やはりmake の最後で止まってしまう。
しかたないので,2.1.119 のソースに再度パッチを当てて試す。しかし,またしても, japanese ディレクトリがないといって止まる。確かにない。で,またしても安直に 2.1.120 のソースから持ってくる。
で,ここでやっと気づいたのだが,最近のパッチは2分割になっていたのだ。最初からソースを作り直し,パッチを当て直して無事 make は終了したが,NTFSのファイル名が化けていることに変わりはなかった。
何と作者からメールの返事が届く。「やはりだめでしたか。」とのこと。make の途中で止まるのは2つともパッチのバグだそうだ。
vfat-jp パッチのスペシャルバージョンの件で,作者が「NTFS 環境がないので,テストできない。」と書いてあったので,きのうの状況をメールする。
Visual Tcl/Tk などというどこかで聞いたような名前のソフトをインストール。要するに,Tcl/Tk のパーツをマウスだけでぐりぐり作れて,ソースを吐き出してくれるものだろう。使ってみると,けっこうおもしろい。あとはパーツの色指定が数値による直接指定ではなくマウスで選択できたらなおよろし。TkDesk みたいにバイナリではなく,すべてテキストのソースなので改造するのもおもしろそうだ。カーネルを 2.1.120 に。vfat-jp パッチのスペシャルバージョンがあり,NTFS の日本語ファイル名も表示できるというふれこみだったから。で,make してみたのだが,しょっぱなから linux/autoconf.h がないといってエラーでコケる。確かにない。これは 2.1.119 のソースから拾ってきて無事通過。で,次に,fs/fat/inode.c が DEFAULT_CODE undeclared といってまたコケる。inode.c に #include "../japanese/japanese.h" を付け加えて通過。これは vfat-jp パッチのバグだろう。で,再起動してみると,見事に NTFS の日本語ファイル名が化けている。設定で文字コードを変えたり,半角カナ→全角変換のオプションを変えてみたりといろいろやってみたが結果は同じ。マウントのときに何かのオプションつけるのかな?
bzip2-0.9.0.tar.gz をインストール。gzip よりずいぶん速度が遅かったのが改善されているそうである。で,make すると↓のエラーで止まる。Slack3.4 + 2.0.35 では正常に make できるところをみると,どうやらこれは KDE や bunzip2 が悪いのではなく,Slack3.5 が「犯人」だろう。/etc/profile にでも CPPFLAGS 設定するだけでいいんだろうが。
で,開発版カーネルでもめでたく ppp できるようになったのだが,なぜかつながりにくく,5回に1回くらいしかつながらない。あとは認証の段階で拒否されてしまう。もしやと思い,ppxp を最新版(ppxp-0.98082821.tar.gz)にかえたらあっさり接続できるようになった。tkppxp はミニコンポのようなかっこいいルックスになっていた。プロキシソフト squid-1.1.22 をインストール。まぁ,スタンドアロンではあまり意味がない気もするが。普通のインストールと違うのは,make install 後に squid -z でキャッシュディレクトリを作ること,squid 専用のユーザ,グループを作ること,rc で起動するときは su squid -c をつけて squid ユーザで起動することくらい。
UNIX USER 8月号の付録CDに付いている KDE beta4 をインストール。なぜか,make の途中で c++ のヘッダファイルがないといってエラーで止まってしまう。そこで,
env CPPFLAGS=-I/usr/local/includeg++ ./configure
で configure すると無事 make できた。それにしても,c++ のヘッダファイルを見つけられないなんて,前のバージョンではなかったのに。Linux も相当メジャーになったんだし。
カーネルを最新版の 2.1.119 に。Linux Memo のページ「make できないかもしれない」と書いてあったが,スムーズに終わる。ただ,ちと最後の番号が縁起悪いか?今まで,カーネル make の際に,make zlilo して kernel is too big のエラーで止まったときは,エラーメッセージ通り make bzimage して手でカーネルをコピーし lilo していたが,make bzlilo でいいそうだ。知らなかった。大タコ。
Linux メモのページにあったのだが,最新版カーネルで IP masquarade するときには,ipfwadm ではなく ipchains を使うらしい。で,双方ではコマンドラインの書式が大幅に違うわけだが,書式の差を吸収する ipchains-scripts なる便利なものがあり,この2つをもらってきて試してみると,2.1.111 あたりから起動時に出ていた ipfwadm のエラーが,ipchains ではきれいさっぱり消えていた。で,さっそく試してみようと ppxp を起動するが,ログインに行く前に回線を切られてしまう...で,作者の真鍋さんのページを見てみると,2.1.118 以降へ対応しているという userlink-0.98a.tar.gz が置いてあったのでさっそく get 。無事に IP masquarade できるようになった。
病気が治ったと思ったら,今度は交通事故で8日から15日まで入院。
で,カーネルを 2.1.116 から 2.1.118 に。 2.1.117 はサウンド関係のエラーでコンパイルできなかった。
先週の金曜日(8月1日)から病気で休んでいた。やっと元気が出てきたので,カーネルをバージョンアップする。2.1.109 から一気に 2.1.114 だ。過去の日記(7月)で,xreadvcd は動くようになった。
音も出るようになった。ただし,モジュールではなくカーネルに組み込み。モジュールにした場合は,リソースをオプション指定して手動でロードしなければいけなくなったのだが,これと kerneld との相性か? resouce busy でモジュールがロードできないのだ。xemacs も日本語メニュー+xim で動くように make できる。コツは,lesstif が入っているので,configure のオプションに --with-dialogs=athena を加えること。motif と違って lesstif では日本語の表示はできないようだ。で,これをつけないと自動的に lesstif のメニューになってしまい,化けてしまうというわけ。もちろん --with-xfs もつける。あと,athena ウィジェットを使うときは,libXaw をデフォルトに戻しておきましょう。ワシは,libneXtaw(3D表示でカッコいいのだが,日本語表示できない→ソースを i18n で grep したらけっこうヒットしたので、ワシがやり方を知らないだけかもしれない)に差し替えていたので文字が化け「おかしいなぁ」と悩んでいたタコだった。