名前の通りの内容です。クマさんがインストールした経過を忘れないように書いたものです。たぶん、ちっとも役に立ちません。過去の日記(7月、8〜9月)
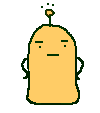
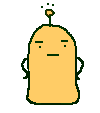
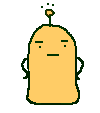
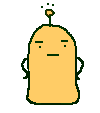
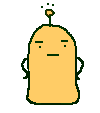
きのう、gcc-2.8.1 が姿を消したなどとタコなことを書いたが、ここ(Ring Server プロジェクトのサーバ。リンクは通信総合研究所に張ってある。ライブラリ一覧はこちら)にあった。探し方が悪いだけだった。archie でも 2.7.x しかひっかからないし、Sunsite や tsx-11 にも egcs しかないので消えたものだとばかり思っていた。
で、make してみたのだが、2.1.126 では原因不明のエラー(cpp の文法ミスだって)で失敗する。2.0.35 の方では何の問題もなく成功。きのう失敗した egcs-1.1b もあっさり make できてしまった。あの苦労はなんだったのだろう。最近、うすうす感じていたのだが、2.1.x の方はライブラリだとかをインストールするときにディレクトリなんかがバラバラで全く秩序が取れていなかった。深く考えずに ./configure ; make ; make install でやってしまうものだからあるものは /usr に、あるものは /usr/local に...で、最初に Slackware をインストールしたときに入ったものと二重に存在するものがあったりして、「あれ、これってどっち使ってるんだっけ?」という状態のものが多々ある。あと、その場しのぎのシンボリックリンク張りまくりとかもある。環境変数設定し直さないと make に失敗したことが多々あったが、これが原因だろう。ディストリビューションの設計を考えて、秩序正しくインストールするべきだった、といっても後の祭り。気分を変えて、Plamo Linux でもインストールして1から出直そうかな...
binutils を binutils-2.9.1.0.15.tar.gz にした。cc を gcc から egcs に換えようと思い、 egcs-1.1b.tar.bz2 と libg++-2.8.1.2.tar.gz を持ってきた。Slackware 3.5 では元々 egcs だったのだが、カーネルを make しなおしたら X が起動しないとか、いろいろ問題が出ていたようだったので、今まで Sunsite から get した gcc-2.7.2.3.tar.gz をずっと使ってきた。
別に gcc に不満があるわけではなく、バグがどうのこうのというわけでもない。まぁ、いいかげん古くなってきたし、egcs もそろそろ落ち着いてきたのではないかと思ったので、換えようと思っただけ。gcc-2.8.1 とどちらにしようか迷ったが、Slackware も egcs だし、gcc-2.8.1 もいろいろ変な話を聞く(そういえば、最近 ftp から姿を消した?)ので、egcs を選んだ。
先日の bash でもそうだが、カーネルのバージョンアップ以上に、シェルとか cc とかの基本的なソフトの入れ換えには慎重になってしまう。事実、INSTALL/faq.html には 2.0 系カーネルの make で問題のあることが書いてある(They use certain asm constructs which are incorrect, but (by accident) happen to work with gcc-2.7.2. だそうだ。2.1 系カーネルは fix されていて大丈夫らしい。)し、カーネルのバグで X が起動しないようなことも書いてある(これも 2.1 系は大丈夫みたい)。KDE も危ないらしい。こんなシビアなもの(まぁ、元はといえばソースのバグなので egcs のせいではないが)を素人の私が使っていいのだろうか。
で、結果はというと make で失敗、ちょん。g++ のところでコケてしまう。また、気のいい gcc-2.7.2.3 との平和な生活が続くことになった。まぁ、そのうち再挑戦してみよう(最近、このパターンが多いな)。
2週間ぶりのごぶさた。カーネル 2.1.126 が出ていた。が、サウンドドライバの make でエラー発生
sb_mixer.c: In function `sb_mixer_ioctl':
sb_mixer.c:357: `SOUND_MIXER_OUTSRC' undeclared (first use this function)
sb_mixer.c:357: (Each undeclared identifier is reported only once
sb_mixer.c:357: for each function it appears in.)
sb_mixer.c:392: `SOUND_MIXER_OUTMASK' undeclared (first use this function)
で、ソースを見てみると確かにそのとおり。sb_mixer.c とか sb_mixer.h とかいじってみたのだが、今度は他の変数で同じような症状が出たりして、結局この2つだけ 2.1.125 のソースと差し替えて make を無事?終了した。なので、2.1.125.99 か? (^^;;;
vfat 日本語化パッチ(vfatjp-0.8.1pre2.tar.bz2 Linux Memo のページへ)も相変わらずちゃんと使える。文字コードが EUC なのに半角カナが表示できるのは本当に不思議。KDE-1.0 をインストール。過去2敗(1敗め、2敗め)の?苦き思い出が脳裏をよぎる。で、過去の教訓に基づき、
env CPPFLAGS=-I/usr/local/include/g++ LDFLAGS=-s ./configure
で C++ のインクルードファイルの場所を教えてやる。
make の途中は kdesupport が warning の嵐。おまけにせっかく新しくしたライブラリが古いヤツに置き換えられてしまったりして、このあたりは依存関係を全くチェックしていない弱みか。ま、Windows みたいに OS 自体が起動不能になったりすることはないのでいいか。あと、kdeutils も ファイルシステムのエラーでコケる。まぁ、OPTIONAL なのでいいかと kwm を起動させると Segmentation fault で仕上げ。見事に3敗目だった。ImageMagick-4.1.3.tar.gz をインストール。./configure すると、png(libpng-1.0.2.tar.gz)と zlib(zlib-1.1.3.tar.bz2)おまけにtiff(tiff-v3.4-tar.gz:2.1.125 のみ fail する)が failed tests になってしまうのはなぜ?
おまけに PerlMagic の make に失敗して止まってしまう。
./configure --enable-shared
で configure するとちゃんと make できる。Netscape Communicator 4.07 だが、けっこう不安定なので、libretto と mobio は 4.06 に戻す。なにせ、ファイルのダウンロードをしようとすると必ず落ちるし、このページを composer で開こうとすると navigator ごと落ちたりすることもあるので、使い物にならない。
gtkglarea-0.6.tar.gz をインストール。Mesalib-3.0 を使っているので、
./configure --with-lib-MesaGL
で configure する。
README の INTRODUCTION には、”GtkGLArea is an OpenGL widget for GTK+ GUI toolkit”だと書いてある。で、インストールしたからといってその時から劇的な変化があるわけではないのだが、サンプルでついてきた 3D のペンギンをマウスでぐりぐり動かして遊んでみた。xscreensaver-3.00.tar.gz をインストール。
./configure --enable-subdir=demos
で configure する。Mesalib-3.0 を使っているのだが、configure のときに”Mesalib-2.6 使ってるみたいだけど、セキュリティ上のバグがあるから 2.7 以降にアップしたほうがいいよ”とメッセージが出るのはなぜ?
README を読む限りでは、メジャー番号が変わった割に目立った変化はないようだ。前使っていた 2.33 では、pipes(NT や 95 OSR2 を使っている人は知っているはず)のバルブやメーターがやたらいっぱい出てきて、仕様(一種の皮肉?)だと思っていたのだが、これはバグで fix されたとのこと。ちと画面がすっきりしてて寂しいか?
ひさしぶりに?デスクトップの話。
gimp-1.0.2.tar.bz2 をインストール。バグフィクス版のようで、Changelog を見てもそうとしか書いてないし、実際使ってみても特に違いは感じない。もちろん、日本語メニューもちゃんと使える(詳しくはこちら)。
最近買った mobio を職場の DHCP サーバに接続するため、dhcpcd-0.70.tar.gz をインストールした(何で mobio を買ったかの顛末はこちら。)。設定も簡単。添付の設定ファイルがそのまま使える(私は最小限に絞り込んだが)。ifconfig で IP アドレスを発行してもらえたのを確認。
自宅では固定のプライベートアドレスを使っているので、両方の環境で使うには環境を切り替える必要がある。Windows なんかだと設定やったあと再起動が必要だったりして,環境の切り替えがタイヘンなのだが、pcmcia-cs には scheme がある。
cardctl scheme 切り替えたい環境名
一発で瞬時に切り替え OK だ。
ところで、dhcpcd といえば、プライマリサイトの神戸大学はディレクトリごとなくなっているし、archie には引っかからないしで、いったいその後どうなっているのだろうか。
wget-1.53.tar.gz をインストール。クマさんのページもファイルが増えてきて(まぁ、見ている人は自分以外にはいないだろうが)、「えーっと、どのファイルとどのファイルをアップロードしてっと...」などと考えるのが面倒くさくなってきたから。ドキュメントを読んでみると、ミラーリングやロボットの機能もあるらしい。でも、名前からして、put ができないなどというオチも十分考えられる。
Netscape Communicator 4.07 と日本語化キットをインストール。目立った点といえば、起動時にひさしぶりに使用許諾同意画面が出たことと、その内容が文字化けしていたこと(^^;;;。初期画面も多少変わっているか。少し使ってみたところ、vje ごとお亡くなりになる回数が多少増えた気がする。おまけに、ファイルをダウンロードすると必ずお亡くなりになってしまうが...
カーネル 2.1.125 が出ていたのでさっそく make する。make xconfig して様子を見てみると「PC110 digitizer pad support」なんちゅー項目が。もしや、と思いヘルプを見てみると、やはりあの「ウルトラマン PC」 PC110 のことだった。うーん、ウルトラマンで 2.1 系のカーネル使っている人がいるんだろうか。カーネル make するのにディスクスペースが足りないような気が...あ、別のマシンで make すればいいだけか。
で、vfat-jp パッチ(vfatjp-0.8.1pre2.tar.bz2)も相変わらずちゃんと使えます。文字コードも相変わらず EUC にしているのだが、半角カナの表示(FD-clone、samba も OK)も大丈夫。感謝感謝。bash-2.02.1.tar.gz と日本語パッチ bash-2.02.1.jpatch(例によって Linux Memo のページ からいただいたもの)をインストール。「bash 入門」(アスキー)によるとけっこう機能変更があったそうなので、どきどきする。INSTALL を読んでみると configure にもいろいろオプションがあり、モノがモノだけに慎重に設定しなければいけないのだろうが、まずは安直に ./configure、make、make install ですます。
bash -version の結果は
インストール前:GNU bash, version 1.14.7(1)
インストール後:GNU bash, version 2.02.1(1)-release (i586-pc-linux-gnulibc1)
で、インストール後の変化といえば、XMODIFIERS が vje になっていても gimp が起動するようになったこと(以前はこうだった)。でも [Shift]+[Space] しても warning が出るだけでやっぱり VJE は使えない。gimp の動作自体は以前より安定しているような気がする。gnus-5.6.9.tar.gz をインストール。readme には configure のオプションなんて書いてないのでそのまま ./configure すると、
・make のときに emacs のディレクトリを探しに行って「lisp がないぞ」とか怒られたり(Makefile の emacs= の行を /usr/local/bin/xemacs にすればよい)、
・トップディレクトリの Makefile に prefix の行がないので、make install のときに / にディレクトリ掘りに行ったりする(サブディレクトリの Makefile にはちゃんと prefix 行がある)
のはバグなんでしょうかねぇ。
で、~/.emacs にパス書いて起動してみると、以前は赤い牛が登場していたのだが黄緑の牛に変わっていた。実は、gnus 新しくしたのは、起動時に
Invalid read syntax: "Integer constant overflow in reader", "1998080701"
などというエラーが出てニュースが読めなかったので、新しいバージョンだったら...と期待したから。でも、同じだった。
で、何でニュースのファイルがこんな大きな番号になっているかというと、jaist の FTP サイトからもらってきたアーカイブをそのまま使っているから。ファイル名は年月日+一連番号2桁になっている。こいつを INN のスプールに突っ込んで読んでいる。
要は当該部分のコードを書き換えてしまえばいいのだろうが、いまいち元気が出ないし、Netscape のニュースリーダではちゃんと読めるので、しばらくそのままにしておこう。
MesaLib-3.0.tar.gz、MesaDemos-3.0.tar.gz をインストール。README によると、このバージョンから OpenGL 1.2 API specification をインプリメントしたそうだ。べつにそれはどうでもよくて、新しいデモが楽しみなだけだったりする。make linux-386-elf で make 一発。xscreensaver-2.33.tar.gz をインストール。今まで使っていた 2.24 と比べると、bubble3d(3D の泡がぶくぶく)、lament(宝箱のようなものがぐるぐる)、の2個のモジュールが新たに入ったようだ。
80 個以上あるモジュールは、そのままでは /usr/local/bin に入ってしまうので、
./configure --enable-subdir=demos
で demos ディレクトリに入れるのはこの日に書いたとおり。
おもしろい機能 ? もある。起動時に「ヒョウタンツギ」(知ってる ? )のようなドクロマークのロゴが出るようになった。gtk+-1.0.6.tar.gz をインストール。もちろん、日本語が使えるように、gtkconv-1.0.6.tgz にあるパッチを当てる。Slackware Linux は locale がちゃんとしてないらしい(他がどうかは知らない)し、Wacom のタブレットも使ってみたいので、
./configure --with-locale=ja_JP.ujis --with-xinput=xfree
で configure し、make する。qpopper のセキュリティホールが見つかったそうなので(私の使い方だとほとんど関係ないのだろうが)、qpopper2.53.tar.Z をインストール。ウチの Slackware 3.5 はシャドウパスワードなので、
./configure --enable-specialauth
で configure しないと、認証されずに悲しい思いをしたり、設定を疑って無駄な時間を使ったりしたのはかくいう私だ。
きのう、きょうと dosemu-0.98.1 で遊ぶ。make がラクになったことよ。設定書き換えずに make 一発だし、Tcl/Tk の設定ソフトはついてるし。で、Windows95 の起動ディスクで hdimage 作ったら起動時にあのロゴが見えるそうなので試してみる。あれ、確かに xdos では見えるけど、kterm から dos 起動したら見えない。おまけに、jfont.sys のロードで「この 16x16 フォントはボク知らない(相変わらずいいかげんな訳だ)」なんちゅーメッセージを出して日本語が使えないぢゃないの。dosemu.conf の書式も以前と全然違うので、どこいじったらいいのかすぐにはわからんし。ま、実用的には 0.66.7 + 日本語パッチ + PC-DOS/J 6.3V( + air craft ) で十分用が足りているので、今後のお楽しみとしよう。ニシオノユウコさんのページからもらってきた愉快なアニメーション GIF は、実は Linux + Netscape Communicator と Win95 + IE 3.02 では見え方が違うものがあることに気がついた。一番左の怪しげなおぢさんは、IE 3.02 では右しか向かないし、手も振ってくれない。
WindowMaker-0.20.1.tar.bz2 をインストール。2番目の数字が上がったときには、過去には設定ファイルの互換性が全くなくなるとかいろいろあったようなので、きのうに引き続きわくわく?する。実際、ChangeLog を見てみるとけっこう変更点が多い。で、起動してみると、苦労して作ったアイコンの配列は無事。何だ、今までと同じじゃないかと思ったが甘かった。今まで気に入っていたメニューの渋いダークカラーが単なるくすんだシルバーになってしまった。フォーカス外のウィンドウのタイトルバーも同様だ。画面がすっかり間の抜けた感じになってしまった。0.19.3 はテーマを変えると日本語メニューが化けたり、色が元に戻らなかったりしたのだが、その点はまだ怖くて試していない。Netscape Communicator の 4.07 が出ていた。日本語化キットが早く出ないかな。
5日というより、6日の 1:00 なのだが、カーネル 2.1.124 が出たのでさっそく make する。展開して 2MB と、かなりでかいパッチだったので心配だったが、何の問題もなく make は終了。最近は、2.1 系のカーネルでも、make できないとか、make できても起動できないとか、起動できてもやたら不安定、とかいうのはなくなってきたようだ。config を見てみると、Solaris の filesystem サポートが追加されていた。FAT や vfat はもちろん、apple に amiga、OS/2 HPFS に NTFS までサポートされているので OS オタクの人でも安心?ファイルシステムといえば、vfat-jp パッチも 2.1.123 のものが使えた。あいかわらず半角カナもちゃんと表示される。感謝感謝。UNIX USER 付録 CD についていた gimp のマニュアルをインストール。HTML 版は bzip2 で圧縮しているのに 16MB もある。「80分で覚える gimp(いいかげんな訳だ)」なるページを見てみると、ページ上の画像だけで 20MB 以上もあり、ローカルのディスクからでのロードも相当な時間がかかる。やー、使いこなせればこんなこともできるんですねと感動。
Wine-980927.tar.gz と日本語化パッチ Wine980927-jp.tar.gz をインストール。ディスクの残り容量が 130MB だったが、まぁ大丈夫だろうと思って make すると、終わった時には残りは 0MB !
WinTach が起動したのでテストしてみると、361.53/C02 だった。Super-π も起動したのでテストしてみると、104 万桁が 14分 4秒。Win95 の記録が 13分39秒だから、まずまずだろう。
Wine の info は XEmacs で作成できなかったので、make したものをそのまま使ったが、なぜかこいつは XEmacs でちゃんと読める。gimp-1.0.1.tar.bz2 をインストール。最初、1.0.0 のソースにパッチを当てたものを make しようとしたのだが、plugins/fli で変数がコンフリクトを起こしたといって止まってしまう。フルソースを持ってきたら何事もないかのように終わる。なぜ?
./configure の途中で「ライブラリがないのでプラグインが make できない」とメッセージを出すので、該当する aalib-1.2.tar.gz と mpeg_lib-1.2.1.tar.gz を Sunsite のミラーから持ってきてインストール。
mew-1.93.tar.gz をインストール。XEmacs のツールバーの Mail アイコンから起動できるように設定する。けっこう便利。日本語 info ファイルがあったので XEmacs で見てみる。すると、info ファイルの先頭以外の node をクリックすると、node があるにもかかわらず、"No such node : " と出て見ることができない(偶然見ることができるものもあるが)ことに気づいた。XEmacs 標準のディレクトリ以外の場所にある info はすべてそうなるようだ。
で、mew のページのこちらに解決方法が書いてある。XEmacs と Emacs とは info のファイル形式に多少の違いがあるらしく,Mew のアーカイブに入っている info をそのままインストールしても読めないそうだ。そこで、XEmacs で mew.texi を読み込み、
M-x texinfo-format-buffer
と実行して、XEmacs で info を作成しなければいけない。また、日本語 info を作成する場合は、 mew.texi の最初の方の パラメータが
@setfilename mew.jis.info
@set jp
となっているのを確認する必要がある。なぜか、
Must be string, vector, or font-instance: #<x-frame"emacs" 0xb4a>
というエラーが出て悩んだが、無視して進めると無事 info ができあがった。あとは保存しておしまい。mew の info が読めないのは、~/.emacs の設定がタコなせいではないかと悩み、elisp の勉強しなくちゃと elisp-manual-19-2.4-jp2.0.tar.gz を get してきた。ところが、上記のような理由だからこいつも読めるわけがない。ますますタコツボにはまってしまった結果となった。XEmacs 上で作り直して一件落着。途中で、「include している index.texi がない」といって止まってしまうが、index-jp.unperm ならあったので、こいつをリネームして解決。
mew(の info)をインストールするためだけに、これだけ時間がかかってしまうとは、クマさんのタコツボ脱出への道のりは遠い。
Netscape Communicator を 4.06 に、日本語化キットも導入。きのう書いた、Composer がアンカー入れたら落ちるというのは変わらない。日本語化してないオリジナル(メニューが英語の状態)のまま起動するとそんなことはないようだ。
autofs-3.1.1.tar.gz をインストール。カーネル 2.0.35 の方にはとうの昔に入れていたので、インストールは超楽勝。やはり、自動マウントは楽だ。ちなみに、kernel automounter のサポートは 2.0.35 では experimental だが、2.1.123(もっと前からだが)では標準だ。過去の日記(7月、8〜9月)このページって、日付にアンカーを入れているのだが、Netscape Composer はこういうフォーマットのアンカー入れると必ず落ちる。
先日の samba の件、Makefile に -DKANJI=\"euc\" と文字コードを EUC に指定して make したら、ちゃんと Windows クライアントで半角カナ文字が表示された。うーん、不思議。