名前の通りの内容です。クマさんがインストールした経過を忘れないように書いたものです。たぶん、ちっとも役に立ちません。過去の日記(7月、8〜9月、10月、11月)ダイジェスト版
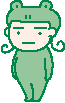
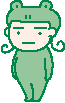
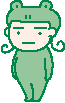
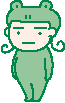
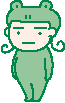
カーネル 2.2.0 pre1 の続き。パッチではなくフルソースなら問題が解決できるかもしれないなどという甘い考えで,10MB 以上あるソースをもらってきた。
1. tulip.c のエラー
DECchip Tulip (dc21x4x) PCI support を built-in にすると,相変わらずエラーで止まる。ま,エラーメッセージのとおり,こんなのいらないんだろう。設定メニューの上にある Generic DECchip & DIGITAL EtherWORKS PCI/EISA でちゃんと動くので,よしとしよう。(んじゃ,何でメニューに出てくるの?という疑問は残るがまぁいい。)
2. make 最後のエラー
これは出なくなった。フルソースの恩恵か?不思議だが,まぁいい。
3. windowmaker が起動不能。afterstep は OK(2.1.132 から)
よく見たら,sygnal 11 を出しているのは X サーバ。バイナリで配布されている X サーバに差し替えたらちゃんと動く。で,X サーバをカーネル 2.2 の環境で make しなおしたら OK。x-tt な X サーバを使っていて,windowmaker が起動しなくなったら,試してみる価値があるかも。vfat-jp パッチも,2.2.0 pre1 に対応した 0.8.2a が出ており,日本語ファイル名の表示は半角カナを含み OK。userlink-0.98a(PPxP で使うドライバ)も使えるし,テレビもちゃんと見える。
カーネルの設定に MTRR があったので,built-in にして make してみた。echo "ベースメモリ番地 メモリサイズ タイプ" > /proc/mtrr してみると,xengine が驚異的に速くなっている。約 1.8 倍だ。windowmaker も,起動時の異様なディスクアクセスがなくなり,静かに起動する。で,新しいカーネルで,めでたく新年が迎えられるかと思ったが,プリンタが壊れて年賀状が書けない...
ついにカーネル 2.2.0 pre1 が出た。プライマリサイトは Access denied due to very high load な状態。
まず,make xconfig がエラーでこけ,make menuconfig して make してみると
tulip.c:2233: #error Code is wrong, and it has nothing to do with 2.2 :-)
で止まる。設定を直すと,今度は make の最後の方で
net/network.a(sock_n_syms.o)(__ksymtab+0x268): undefined reference to `csum_partial'
net/network.a(core.o): In function `csum_partial_copy_fromiovecend':
...
net/network.a(ipv4.o): In function `ip_fw_masquerade':
...
old-checksum.o(.text+0x34): undefined reference to `csum_partial_copy_generic'
で終わり。gcc-2.7.2.3 でも egcs-1.1.1 でも同じ。
libc-5.4.46.tar.bz2
net-tools-1.49.tar.bz2
util-linux-2.9g.tar.gz
を入れてみたけど同じ。
今は 1:00 なのだが,24日には違いないので 24日にした。クリスマスプレゼントか ? カーネル 2.1.132 が出た。2.1 系カーネルの儀式である,Makefile の "SMP=1" をコメントアウトする必要がなくなった(もちろん,SMP の人は関係ない話だが)。設定メニューに移ったのだ。他に,IrDA 関係の設定が新設されたりとか,けっこう新機能が多い。
で,make したあと起動してみたのだが,何と windowmaker が signal 11 で落ちてしまう(afterstep はちゃんと起動する)。→この日に解決。バイナリ配布の X サーバを使っている人には関係ない話だろう。で,泣く泣く 2.1.130 に戻した。世間の人はきょうはこんなことはやっていないのだろう。クマさんは残業で帰宅は 25日になってから,じゃないのかな。
BeOS R4J をインストールした。この日,インストールできないと悩んでいるが,原因はしょうもないことだった。
[本体]ーケーブル1mー[外付ケース]ーケーブル1mー[外付ケース2]
↑こいつを外した。
で,外付のケーブルを1本にしてみたら,あっけなくインストールできた。ケーブル長の関係でタイミングがずれ,正常に SCSI 機器が動作しなかったのだろう。確かに,Ultra SCSI のケーブル長の合計は 1.5m 以内と規定されているが「SCSI-2 のモードだったら大丈夫だろう」と上記のような結線にして使っていた。実際,Linux,FreeBSD,Windows95,WindowsNT では一応動作していたのだが,Solaris や BeOS ではだめだった。ドライバが規定通りの作りなのだろう。で,BeOS 用にこんなページをつくってみた。この日に,カーネル 2.0.36 が gcc-2.7.2.x でないと素直に make できない話を書いた。翌日には,Slackware 3.6 では 2.0.36 は make できるのかなどとよけいな心配をしている。UNIX USER 1月号を見てみると,gcc-2.7.2.3 に戻っているようだ。いいことなんだか,どうなんだか。ま,とりあえず 2.1 系の環境(egcs ベース)は Slackware 3.5 ベースでよいことになり,一安心か。
BeOS R4 を買いに行った。どこかの OS みたいにカウントダウンなんかやったみたいなので,混雑をさけて夕方に行ったのだが,それでもレジには常時20人近い人が並んでいる状態。皆,箱入りの新規版パッケージを手にしている。クマさんはアップグレードなので箱なし,七宝焼きのエンブレムがおまけで付き,3600 円 + 税。
で,インストールなのだが,ブート FD のブートメッセージがでて,CD をちょろっと読みに行ったかと思ったらそのままハングして終わり。使用機器はこのとおり。SCSI の設定を変えたり,CPU のクロックを落としたりいろいろやってみたのだが,どうにもならない。ここと比べてみても,CPU が Celeron だったり,チップセットが Intel ではなく VIA だったり,CD-ROM がナカミチの 4連装だったりする以外は,全く普通のマシンだと思うのだが。→この日に解決
で,インストールした,とは書けない。しかたないので,エンブレムだけゼロハリのアタッシェに貼った。デーモン君とペンギン君のエンブレムの間に Be のエンブレムを貼った変なゼロハリを持っている,小太りなサラリーマンが深夜の電車に乗っていたら,それはたぶんクマさんだ。
xtt-1.1.tar.gz(リンクは塩崎さんのページ)
X サーバで TrueType フォントを使えるようにしたパッチ。X のソースにパッチを当てて make して X サーバを作る。クマさんはこれがないと生きていけない。バグ修正の他,ベースとなるソースのバージョンが XFree86-3.3.3 になったそうだ。1.0 に 3.3.3.の組み合わせでもこの日にちゃんと make できたのを確認している。今回,X333servonly.tgz + xtt-1.1.tar.gz で make World にかかった時間は 23分。速い速い。
egcs-1.1.1.tar.bz2(リンクは通信総合研究所のミラー)
gcc --version は egcs-2.91.60 になった(1.1b は egcs-2.91.57)freetype-1.2.tar.gz(リンクはプライマリサイト,ミラーはここ)
../lib/.libs/libttf.so: undefined reference to `dgettext' でコケる。きのう付けの freetype-current.tar.gz もそう。lesstif-0.87.0.tar.gz(リンクはプライマリサイト)
mofit 互換ライブラリ。とりあえず,make できるのは確認したけど,インストールはしていない。pcmcia-cs-3.0.6.tar.gz(リンクはプライマリサイト)
Linux で pcmcia カードを使うときになくてはならないのがこれ。ここを見ると,libretto の FD が使えるようになったようなことが書いてあるんだが,ethernet ばっかりで FD はほとんど使わない(どこに置いたか忘れてしまった)ので,あまり関係ないか。今後リリースされるディストリビューションでこいつが組み込まれると,インストール時に FD が使えるようになることでしょう。クマさんはこうやってインストールした。この日,「CPU の動作クロックはどうやって調べたらいいのだろう」とタコな悩みを持ち,翌日には DOS のツールなんて使って調べて喜んだりしているが,やはり大タコだった。
cat /prov/cpuinfo 一発だった...
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 6
model name : Celeron (Mendocino)
stepping : unknown
cpu MHz : 451.065651
cache size : 128 KB
(以下,省略)
Linux って,本当に便利っすねぇ。Nmail(ホームページはここ,クマさんの紹介はここ)の新バージョンが来年1月に出るようだ。Tcl/Tk ベースの現行バージョンから,GTK ベースとなり,かっこよく高速になるみたいで,大変楽しみ。そういえば,新バージョンアナウンスのページのロゴはいかにも gimp で作りましたって感じだ。
出るといえば,XEmacs-21.0 は8月から「リリースは夏! 若干ディレイしています」という状態のまま年を越そうとしている。ひょっとして,「夏」って来年の夏のことなのかなぁ...
ImageMagick-4.1.6.tar.gz (リンクはプライマリサイト)
README に書いてあるページは存在しない。で,探すと上記リンクにページがあり,タイトルロゴの下には SPAM お断りのマークが。
4.1.5 くらいから,./configure で jpeg と tiff のテストが fail しなくなった。めでたしめでたし,といきたいが make の最中に PNG のコードでエラーを出して止まってしまうため,
./configure --with-png=no --enable-shared
で PNG サポートを外してやらないと make できなくなってしまった。BeOS R4J のアップグレード登録をした(きのうまで)。R3J は持っているのだが,何と SCSI 未サポートのため,インストールできなかったのだ。R4J から SCSI をサポート。ここを見ると,Millenium G200 も使えるようだ。デジタルメディア制作に特化した OS とのことなので,今から楽しみ。
帰宅時にいつも缶ビールを買っているコンビニ(自動販売機が使える時間帯には帰宅できないのだ)のレジに,情報ディスプレイがついている。ある日,職場でいつも見ている見慣れたダイアログボックスが出ていて,コケていた。店員は当然復帰できるはずもない。は,は,は。Linux 使えばいいのに。
WindowMaker-0.20.3.tar.bz2(リンクはプライマリサイト)
Next STEP みたいにかっこいいウィンドウマネージャ。12/03 付けでリリースされたとホームページに書いてあったので,とりあえずダウンロード,インストールしてみた。インストールの方法とスクリーンショットはこちら。Changelog を見てみたら,この日書いた不具合(bug ではなく problem だそうだ)は fix されているようだ。あと,Window Shortcuts などという言葉が気になるところ。xosview-1.6.1.tar.gz
Linux Memo のページにあったので,とりあえず make してみたら,2.1 系カーネルでも NET がちゃんと表示されるようになっていた。
xawtv-2.32.tar.gz(リンクはダウンロードディレクトリ)
もうすぐ 2.33 が出ると書いてあった。2.31 は私の環境ではエラーで make できなかった。前回の記録と Linux-PC でテレビを見る方法を簡単にまとめた文章。
きのう、「Millenium G200 に変えたら TV がコマ落ちして...AGP が悪いのでは...」などと見当違いなことを書いたが、これは間違い。xawtv を make して、テストするべぇとシェルから起動すると...
WARNING: v4l and dga disagree about the framebuffer base
WARNING: you probably want to insmod the bttv module with "vidmem=0xec0"
WARNING: overlay mode disabled
これが原因だった。つまり、フレームバッファのベースがわからないので Bt848 本来のオーバレイモード(CPU を介しないダイレクト転送)で起動できなかったわけ。どうりで、モロに CPU パワーを使ったわけだ。bttv/doc/PROBLEMS には「X -probeonly で起動して、メッセージからメモリアドレスを取得して、”insmod bttv メモリ番地”しろ」と書いてある。そのとおりにしたらばっちり解決。やはり、ドキュメントはしっかり読みましょうね、という当たり前のことを再認識したタコなクマさんであった。ppxp-0.98112523.tar.gz(リンクはプライマリサイト)
ひさしぶりにページを訪問したら新しいのが出てた。この日に問題が出ていた 2.1 系カーネルソース関連のコンパイルエラーはちゃんと修正されている。
最近、Linux 人口が増えたのに伴い、readline がないとか(クマさんもこの日にエラーを出した。ちなみに、ちゃんと自分で解決している)、curses ってなんですかとかいうタコメールが多いらしく、新たにタコ対策のページができていた。まなべさんも大変だ。そのくらい自分で解決できないようなら、ソースから make するのはやめた方がいいと思う。バイナリパッケージもちゃんと用意されているのだから。少なくとも、エラーメッセージをファイルに落としたりする方法をまなべさんにメールして聞くなどというのは、非常識ではないだろうか。xlevel-0.8c.tar.gz
サウンドカードのレベルを表示するかっこいいレベルメータ。どこから持ってきたか忘れてしまった。vje の製品版をインストールした。製品そのものは買っていたのだが、インストールしていなかったのだ。Composer で日本語入力しているとき、β版だとタイピングについていけずに入力結果が飛んでしまうことがあったが、製品版ではさすがに大丈夫。ATOK 風のキー操作にも簡単に変更でき、日本語入力の能率は劇的に改善された。その他の細かい不具合も改善されているようだ。もっと早く入れればよかった。バックスからアップグレード用のパッチ(製品版専用。ここにある)も出ているし、初回限定の安いパッケージもまだ在庫があるみたい(ぷらっとホームで見た)だ。
秋葉原に突撃して Millenium G200 8MB AGP を get してきた。TWO TOP で日本語版箱入りが¥19,800-。最近、すっかり物欲の権化だ。で、ちゃんと使えるのは確認した。xengine のスピードはふつーの Millenium PCI と変わらない。xscreesaver の atlantis ではクジラやイルカがスムーズに泳ぐようになり、ビデオ CD の再生はスムーズになった。
疑問点が若干...
・X の設定で、xf86config だと G200 が出てくるのだが、XF86Setup だと MilleniumII AGP までしかでてこない。どちらでも、ちゃんと動くのだが。ちなみに、XF86Config の Device は xf86config と XF86Setup で異なり、ここだけ書き換えると(MilleII → G200 とか)X が起動しない。
・テレビがコマ落ちするようになった。おまけに、CPU パワーも食うようになってしまった(xload で一目盛りくらい)。以前はカーネルコンパイル中でも普通にテレビが見れたのだが、CPU 負荷が増えるととたんにコマ落ちが激しくなる。カーネルコンパイル自体もテレビを見ながらだと5割くらいよけいに時間がかかる(これが一番痛い)。AGP バス自体が相当 CPU パワーを要求するのでは、と疑っている。
→大ウソ。原因は翌日解決。で、普段使うには PCI のふつーの Millenium の方か快適かも(^^;;;
→上記のウソに伴い、これも取り消し。カーネル 2.1.131 が出ていたのでさっそく make。今回も vfat-jp パッチはちゃんと使える。vfat-jp パッチといえば、0.8.2 が出ていたがまだ使っていない。
このページを作っていて気がついたのだが、2.1.131 はどうも vfat ファイルシステムの扱いがうまくないようだ。保存しようとしたらエラーが出て失敗したり、保存失敗後にファイルが行方不明になったりする。行方不明になった?ファイルは 2.0.36 できちんと読み込むことができる(ただし、ファイルの一部が欠落していたが)。このままだと危ないので、そうそうに 2.1.129 に戻した。
XFree86-3.3.3 で NeoMagic のチップがサポートされたので、mobio の X サーバを RedHat 製(以前はこれを使うか Acceralated X を使うしかなかった)から XF86_SVGA に入れ換えてみた。xengine を起動してみると、1割程度スピードが上がっている。もちろん、16bpp も OK だ。NeoMagic のチップを搭載したノートを使っている人は、もちろんバージョンアップするしかないだろう。Slack3.4 や 3.5 ベースの人(要するに、XFree86-3.3.* の人)は XF86_SVGA だけ入れ換えてもいいだろう(もちろん、きちんと設定ができることが条件だが)。カーネル 2.1.130 が出ていたので、さっそく make。vfat 日本語パッチ(vfatjp-0.8.1.tar.bz2 の ntfs 拡張版)ももちろん当てる。vfat の日本語ファイル名表示は半角カナを含めすべて表示される。samba ももちろん OK だ。ntfs の方は相変わらずちと変な表示になる。状況はメールしてあるので、近々進展があるかも。
X333servonly.tgz に xtt-1.0.tar.gz のパッチを当ててみた。問題なく当たり、reject もされてない。make World してみた。前回は1時間半以上かかったが、今回は30分少々で終了。Celeron 様々だ。過去の日記(7月、8〜9月、10月、11月)ダイジェスト版
できあがった X サーバのパーミッションを直し、/usr/X11R6/bin にコピーして使ってみる。本来は、X 全体を 3.3.3 にアップグレードしたあとサーバを差し替えるのだろうが、時間がない(今は am 1:00)。ちゃんと X が起動し、もちろん TrueType フォントが使える。
tomato マザーも AGP スロットが空いて寂しそうだし、Millenium G200 に対応した XFree86-3.3.3(x-tt 対応)の X サーバも make できた。これは、秋葉原に突撃する以外ないではないか!(いつじゃ)